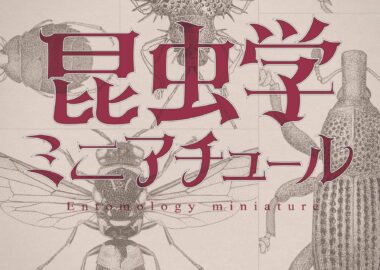~ シカ食害問題 ~
ポイント
・シカ不嗜好性植物のアセビが繁茂している場所と繁茂していない場所の周辺環境と土壌微生物相を比較解析した結果、光環境は暗くなり、他樹種の発芽や成長を妨げる可能性のある腐植の量も増加していました。
・さらに、土壌微生物相を比較解析すると、樹木の成長等を手助けする外生菌根菌の相対存在量がアセビの繁茂によって減少しており、外生菌根菌と共生する樹木にとって定着しづらい環境になっている可能性がありました。
・本研究によって、シカ不嗜好性植物のアセビが繁茂することでも森林の更新阻害が起きていることが分かり、シカ食害による森林の更新阻害をより深刻化する恐れがあることを示していました。本研究成果は、シカ不嗜好性植物のアセビ繁茂についての生態系メカニズムの理解を促進させると共に、今後の森林管理や生物多様性保全について基礎的な知見を提供するものです。
概要
宮崎大学研究・産学地域連携推進機構テニュアトラック推進室の徳本雄史准教授と、九州大学大学院農学研究院の片山歩美准教授の研究チームは、九州山地におけるシカ不嗜好性植物のアセビの繁茂にはシカの食害に伴う森林の更新阻害の問題をさらに深刻化する恐れがあることを明らかにしました。
九州山地では、シカ等によって森林下層の植物が食べられ、一部のエリアでシカが好んで食べないシカ不嗜好性植物(※1)の繁茂が見られています。今回このシカ不嗜好性植物の繁茂による周辺環境と土壌微生物相(土壌内における微生物の集合)の変化を調査したところ、光環境が暗くなり、土壌中の菌相も共生菌類のうち外生菌根菌(※2)の相対的な存在量が低下していたことが分かりました。アセビが繁茂することによって他の樹木の定着が阻害されているため、森林の更新阻害の要因になっている可能性があります。以上の結果は、シカ食害による森林の更新阻害の問題がシカ不嗜好性植物の繁茂によって深刻化する恐れがあることを示唆しています。
用語解説
(※1)シカ不嗜好性植物:シカが採食しない、または採食頻度が低い植物。葉が硬い、トゲがある、植物器官中に有毒な物質を含むといった特徴を持っているためシカは好んで食べない。国内で135種類ほどは不嗜好性植物とされる。
(※2)外生菌根菌:植物の根に感染し、植物が養分を受け取るのを手助けしている共生菌類の一種。菌類は植物が作る光合成産物を受け取ることで生きている。外生菌根菌は主にブナやモミなどの樹木と共生関係を構築することが知られている。
詳細
詳細はプレスリリースをご参照ください。