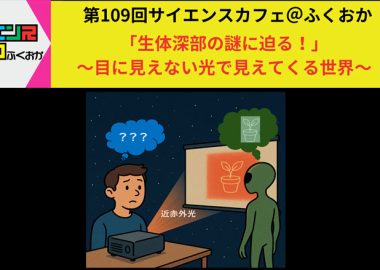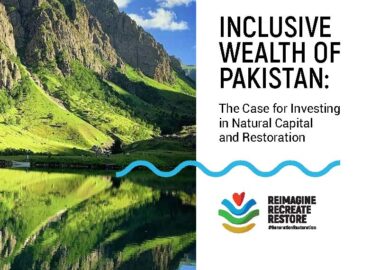-1950 年代から米国で利用されてきた抵抗性遺伝子を世界で初めて明らかに-
農学研究院
穴井 豊昭 教授
概要
ダイズ葉焼病は温暖地を中心に広く発生するダイズの病害です。農研機構は、70年以上前から米国等でダイズ品種の育成に利用されてきたダイズ葉焼病抵抗性遺伝子rxpを世界に先駆けて特定しました。さらに、この遺伝子を持つダイズを効率的に選抜するDNAマーカーを開発しました。農研機構では、開発したDNAマーカーを利用してこの病害に対する抵抗性品種の育成を進めています。
ダイズ葉焼病1)(以下、「葉焼病」という。)は温暖湿潤な気候で細菌の感染により発生するダイズの病害です。葉の表面や裏面に淡黄色から淡褐色の斑点を生じ、発病が激しい時は、葉全体が淡黄色になり、落葉や枯死により、減収や小粒化による品質低下に至ります。農研機構では、この病害に対する抵抗性遺伝子rxp(以下、「抵抗性遺伝子」という。)を特定してDNA配列を明らかにし、葉焼病抵抗性を日本のダイズ品種に導入するためのDNAマーカー2)を開発しました。
米国では1950年代に葉焼病の病斑がほとんど出ない病害抵抗性を有する育種素材を利用して品種開発がすすめられた結果、ほぼすべての品種が葉焼病抵抗性となっています。病害抵抗性に関しては、しばしば、病原菌が急速に進化することで抵抗性品種が感受性になってしまう現象である抵抗性崩壊が見られますが、北米で利用されているこの葉焼病抵抗性にはこれまで70年間に渡って抵抗性崩壊は起きず、安定して強い抵抗性を示す遺伝子です。今回開発したDNAマーカーにより日本の品種育成でも本遺伝子の利用を進めます。
我が国では今まで葉焼病抵抗性に着目した育種が行われてこなかったことから、日本品種の多くは葉焼病抵抗性遺伝子を持っていませんでした。しかしながら、葉焼病は温暖湿潤な気候で多発することから、近年の栽培期間の高温傾向や暴風雨の頻発・激化に伴い、日本でも発生地域が広がり、発生程度の激甚化も懸念される状況となってきました。このため農研機構では、この研究で開発したDNAマーカーを活用することで、葉焼病に対して強く安定した抵抗性を持つ品種の育成を拡大します。
用語解説
(1)ダイズ葉焼病
温暖で湿度の高い気候で、細菌の一種Xanthomonas axonopodis pv. glycines(Xanthomonas campestris pv. glycines)の感染により葉に淡緑の小さな斑点が現れ、次第に中央部が褐色、周囲が黄色の病斑となります。細菌は台風などの風雨によって飛散して広がり、激しく発病すると葉全体が淡黄色になり、落葉さらには、枯死します。
2) DNAマーカーを用いた選抜
品種間でのDNA配列の違いを検出する目印をDNAマーカーと言います。新品種を育成する際、実際に育てた植物で病気に対する強さ(抵抗性)を判定するのは非常に手間がかかります。しかし、例えば畑に種まきする前の種子(豆)の一部を削ってDNAを抽出し、抵抗性遺伝子の有無を判別できるDNAマーカーを使うことにより、抵抗性のダイズ種子を選び出した上で、栽培や交配に利用することができます。
詳細
本研究の詳細はこちらをご参照ください。