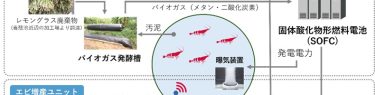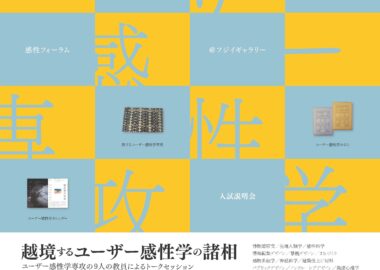応用力学研究所
木下 稔基 助教
核融合炉の革新的な運転シナリオの確立へ
概要
フュージョンエネルギーの実現には、磁場のカゴで高温のプラズマ(※1)を保持し、核融合反応を起こす必要があります。ところが、プラズマ中に存在する不規則で微視的な揺らぎ(乱流※2)により、プラズマが磁場のカゴから流れ出てしまいます。そのため、乱流の物理特性を理解し、それを抑制することは重要な課題です。九州大学応用力学研究所(福岡県春日市)の木下稔基助教、核融合科学研究所(岐阜県土岐市)の田中謙治教授、京都大学大学院エネルギー科学研究科(京都府宇治市)の石澤明宏教授らの研究グループは、大型ヘリカル装置(LHD)(※3)において、レーザーを用いた高精度計測により、特定の条件において乱流が抑制される現象を観測しました。さらに軽水素プラズマと重水素(※4)プラズマの比較実験およびスーパーコンピューターを用いたシミュレーションにより、乱流の抑制は乱流の種類が変化する際に起こることが明らかとなりました。本研究結果は、乱流抑制のための核融合炉の革新的な運転シナリオの確立や炉設計への応用が期待される成果です。
この研究成果をまとめた論文がPhysical Review Lettersに6月7日に掲載されました。
用語解説
(※1)プラズマ
固体、液体、気体に次ぐ物質の第四の状態。気体に更にエネルギーを与えると原子は電子とイオンに分離し、プラズマとなる。
(※2)乱流
プラズマの密度や温度の不均一性が引き起こす、密度、温度、電位の不規則な揺らぎ。特に、数センチメートルから数十マイクロメートルの微小な乱流はプラズマの粒子や熱の拡散を引き起こすと考えられている。
(※3)大型ヘリカル装置(LHD)
核融合科学研究所の実験装置で、超伝導コイルを用いた世界最大級のヘリカル型装置。我が国独自のアイデアに基づくヘリオトロン配位と呼ばれる磁場配位を採用し、二重らせん状のコイルを用いてねじれた磁場構造を形成する。トカマク型装置とは磁場構造が異なっており、特徴を活かしたユニークな研究を行うことができる。1998年から実験を開始し、2017年には核融合炉で必要とされるイオン温度1億2千万度のプラズマの生成に成功した。LHDはLarge Helical Device の略。
(※4)重水素、三重水素
水素には原子核中に陽子を一つ持ち、中性子を持たない軽水素(元素記号H)、陽子一つと中性子一つを持つ重水素(元素記号D)、陽子一つと中性子二つを持つ三重水素(元素記号T)があり、これらは水素同位体と呼ばれている。自然界における水素の存在比は、軽水素が99.985%、重水素が0.015%で、三重水素はほとんど存在しない。燃料となる重水素は海水から取り出すことが可能であるが、三重水素は海水からリチウムを取り出し、核融合反応で生成される中性子と反応させることで三重水素を生成することが可能である。
研究に関するお問合せ先
詳細
本研究の詳細はこちらをご参照ください。