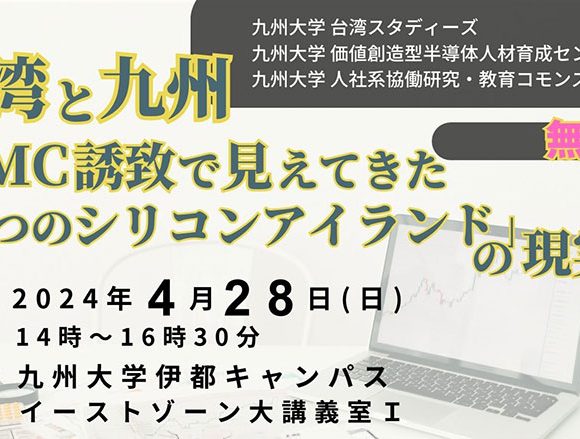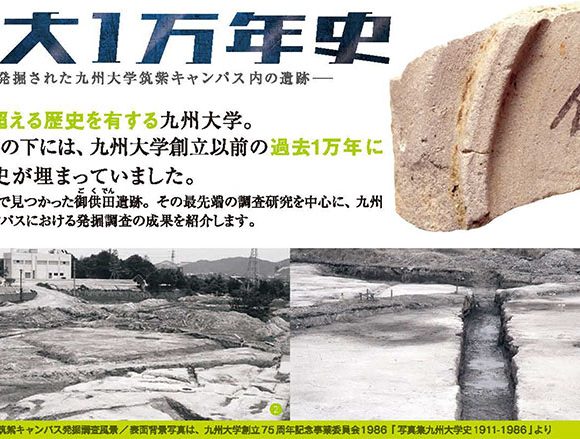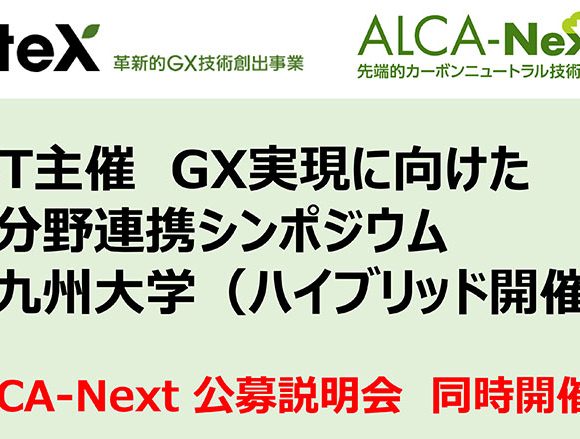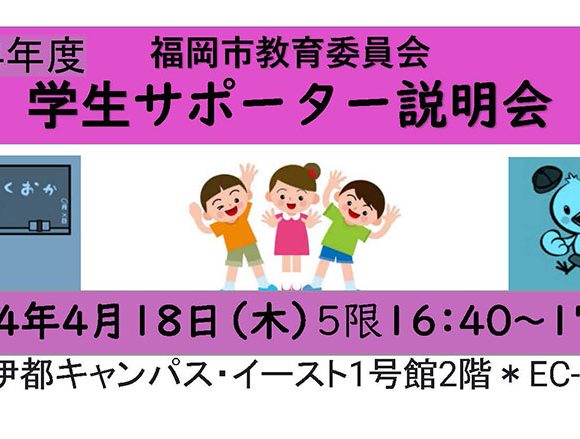- ホーム
- お知らせ
お知らせ
-
【4/28開催】台湾と九州 TSMC誘致で見えてきた「二つのシリコンアイランド」の現実味: 林宏文氏講演会
-
乳児股関節脱臼を激減させた予防運動の価値をライフコース疫学で解明
-
【4/27~6/16】九州大学総合研究博物館2024年度公開展示「九大1万年史ー発掘された九州大学筑紫キャンパス内の遺跡ー」
-
九州大学×TSMC 包括連携の覚書を締結
-
【5/19開催】「第九」日本人初演100周年記念事業公開講演会③
-
九州大学が、三井不動産、日鉄興和不動産とともに「次世代GX産業集積研究部門」を新設
-
【4/22開催】GX実現に向けた異分野連携シンポジウム@九州地区
-
【4/18開催】「福岡市教育委員会学生サポーター制度」R6年度春季説明会
-
無線電力伝送システムの性能をAIで全面的に予測
-
大腸がん発がんにおける免疫寛容を引き起こす仕組みを同定
-
【5/22開催】九州大学人社系副専攻プログラム SDGsセミナーvol.6
-
赤ちゃん星の”くしゃみ”を捉えたか?