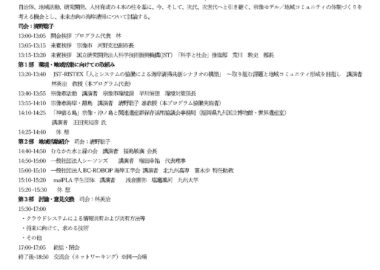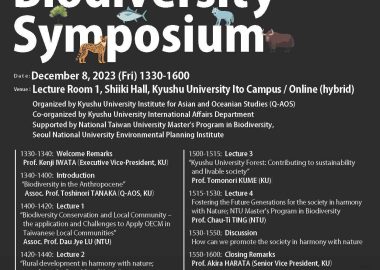〜 海岸性ハネカクシ科甲虫の新種を発見 〜
九州大学大学院生物資源環境科学府博士課程の劉沺沺(リュウテンテン)大学院生(研究当時)、同大学総合研究博物館の丸山宗利准教授らは、うみねこ博物堂の小野広樹氏の協力のもと、海にすむ昆虫の一群である海岸性ハネカクシ科甲虫の新種を発見しました。
昆虫は地球上のさまざまな環境に進出したもっとも多様な生物であることは良く知られていますが、海にも昆虫がいると言うと驚く人が多いでしょう。様々な要因により、海岸や海に住む種の数(海岸性昆虫)は非常に限られおり、ほとんどの種は昔からの環境が残された海岸にのみ生息することができます。しかし現在、護岸工事による自然海岸の消失や海洋汚染、海岸への車の乗り入れ等により、多くの種が激減、あるいは絶滅の危機に瀕していると考えられています。
海岸性昆虫には、満潮時に水没する潮間帯に生息する特殊な種がいます。そのなかでもハネカクシ科甲虫の仲間はもっとも多様性の高い一群ですが、未知の種が多く、丸山准教授らは日本産種の分類学的研究を長年続けてきました。今回、潮間帯性ハネカクシ科甲虫の一群であるナギサハネカクシ属の分類学的研究を行い、合計17種を認め、9新種を発見しました。本属はインド洋から太平洋の沿岸に広く生息しますが、日本はもっとも多様性が高い地域となります。また、昆虫は通常、翅の発達した種ほど分布が広いことがわかっていますが、本属の種は後翅の退化した種ほど広い分布を持つという、非常に珍しい傾向があることも示唆されました。
本研究成果は、2021年(令和3年)5月7日(金)(日本時間14:00)付けでチェコの国際学術誌「Acta Entomologica Musei Nationalis Prague誌」に掲載されました。
詳細
九州大学プレスリリースをご参照ください。